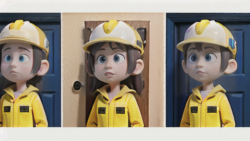 防犯グッズ
防犯グッズ ドアスコープ: 防犯上の注意点と対策
玄関ドアに取り付けられた小さなレンズを通して、訪問者を室内から確認できる装置、それがドアスコープです。ドアアイとも呼ばれ、アパートやマンションといった集合住宅を中心に、多くの住宅で標準的に設置されています。ドアスコープの最大のメリットは、ドアを開けずに訪問者を確認できるという点にあります。知らない人が訪ねてきても、室内から安全に相手を確認することができます。特に一人暮らしの方や、夜間の一人歩きが心配な小さなお子さんを持つ家庭にとっては、安心感を高めるための必須アイテムと言えるでしょう。また、近年では従来のシンプルなレンズタイプだけでなく、広角レンズを採用したタイプや、カメラ機能を搭載したデジタルタイプなど、様々な機能を持ったドアスコープが登場しています。広角レンズタイプは、より広い範囲を確認できるため、死角を減らし、より安全性を高めることができます。デジタルタイプは、訪問者を録画できるため、不在時の訪問者確認や、防犯対策としても有効です。























