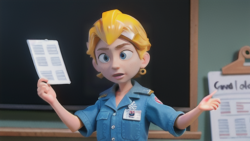水害への備え
水害への備え いざという時のために!一時避難場所を知ろう
- 身近な安全確保の場、一時避難場所とは?いつ起こるか分からない地震や火災などの災害。突然の災害時、あなたの命を守るためにまず最優先すべきこと、それは身の安全を確保することです。そのために重要な役割を果たすのが「一時避難場所」です。一時避難場所とは、災害が起きた直後に、身の危険を感じた際に一時的に避難する場所のことです。また、大規模な火災などが発生した際に、指定避難場所(広域避難場所)へ集団で移動する際の集合場所としても利用されます。一時避難場所には、地域の公園や学校、公民館、広場など、住民にとって身近な場所が指定されていることが多いです。日頃から、自宅や職場、よく行く場所の近くにはどのような場所が一時避難場所として指定されているか、確認しておくことが大切です。いざという時に慌てしまわないよう、家族や近隣住民と避難経路や集合場所について話し合っておくことも重要です。一時避難場所は、あくまで一時的に安全を確保するための場所です。災害が収束した後、自宅が無事であれば帰宅することになりますし、被害が大きい場合は、指定緊急避難場所(避難所)へ移動する必要がある場合もあります。