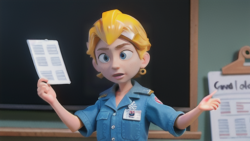水害への備え
水害への備え 津波来襲時の司令塔!津波現地指揮所とは?
- 迫り来る津波への備え地震発生後、津波の発生が予想される場合、一刻も早く安全な場所へ避難することが最優先です。 沿岸地域では、津波は家屋や道路を破壊し、人々の生活を根底から覆すほどの甚大な被害をもたらす可能性があります。 日頃からの備えと、的確な情報収集、そして迅速な判断と行動が、あなたの命を守る上で極めて重要となります。まず、お住まいの地域のハザードマップを確認し、津波発生時の安全な避難場所とそこまでの経路を把握しておくことが重要です。 家族構成や身体状況に合わせて、安全かつ迅速に避難できる経路を選びましょう。また、いざという時に備え、非常持出品の準備も怠らないようにしましょう。飲料水、食料、懐中電灯、ラジオ、救急用品など、数日間生活できるだけの物資を揃えておくことが大切です。地震発生後、津波警報や注意報が発令された場合は、速やかに避難を開始しましょう。 テレビやラジオ、防災無線などから正確な情報を得るように心がけ、周囲の人たちにも情報を共有し、助け合って行動しましょう。津波は繰り返し襲来し、第1波が小さくても、後から大きな波が来ることもあります。安全が確認されるまでは、決して海岸や河口付近に近づかないようにしてください。津波への備えは、自分自身と大切な人の命を守るための、欠かすことのできない行動です。 日頃から防災意識を高め、いざという時に適切な行動をとれるよう、しっかりと準備しておきましょう。