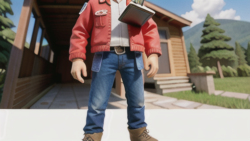地震について
地震について 大地震への備え:命を守るために
- 大地震とは大地震とは、マグニチュード7以上の非常に強い揺れを伴う地震のことを指します。この規模の地震が発生すると、私たちの暮らす地域に甚大な被害をもたらす可能性があります。 まず、激しい揺れによって、建物が損壊したり、倒壊したりする危険性があります。特に、古い建物や耐震基準を満たしていない建物は、大きな被害を受ける可能性が高くなります。また、建物だけでなく、道路や橋などのインフラ設備にも被害が及び、交通網が遮断される恐れもあります。さらに、大地震は、地盤の弱い地域では地滑りを引き起こす可能性があります。地滑りは、住宅地や農地を飲み込み、人命や財産に大きな被害をもたらします。また、海岸に近い地域では、巨大な津波が発生する危険性もあります。津波は、沿岸部を襲い、家屋や建物を破壊し、多くの人命を奪う可能性があります。大地震は、いつどこで発生するのか、予測することが非常に困難です。そのため、私たち一人ひとりが、日頃から地震への備えをしておくことが重要です。家具の固定や非常持ち出し袋の準備など、できることから始めましょう。