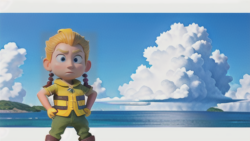水害について
水害について 海からの脅威:波浪への備え
海面に生じる波のうち、風の影響によって発生するものが波浪と呼ばれ、私たちにとって身近な存在です。波浪は、その場で生まれたばかりの「風浪」と、遠くから伝わってきた「うねり」の二つに大きく分けられます。風浪は、その場所で吹いている風によって直接的に生じる波です。風の力を受けて波立ち始めるため、生まれたばかりの風浪は、比較的波の高さが低く、不規則な形をしています。まるで池に小石を投げ込んだときのように、様々な方向に波が広がっていく様子が観察できます。一方、うねりは、遠方の海域で発生した風浪が、風の影響を受けずに伝わってきたものを指します。発生源から長い距離を旅してくるため、波長が長く、規則的で滑らかな波面を持つのが特徴です。海岸に打ち寄せる波は、ほとんどの場合、うねりによってできています。このように、波浪は風との関係性によって、その姿を変えます。波の種類を見分けることで、現在の海の状態や風の強さなどを推測することができます。