圧挫症候群:長時間の圧迫がもたらす危険

防災防犯を教えて
「圧挫症候群」って、具体的にどんな時に起きるのですか?

防災防犯の研究家
例えば、地震で家具の下敷きになったり、事故で長い時間車に閉じ込められたりした際に起こることがあります。

防災防犯を教えて
そうなんですね。家具の下敷きになった場合は、助け出されれば大丈夫なのではないですか?

防災防犯の研究家
実は、助け出された後も注意が必要です。急に圧迫から解放されると、体の中に溜まっていた有害な物質が流れ出し、腎臓などに悪影響を及ぼす可能性があるのです。
圧挫症候群とは。
「防災・防犯に関係する言葉である『圧挫症候群』について説明します。これは、手足が長時間押しつぶされたり、長い間体を動かせなかったり、股関節や肩関節を無理な形で長時間曲げ続けたりすることで起こる病気です。
この病気は、大きく分けて二つの段階で体に悪い影響を与えます。
まず、長時間押しつぶされることで、体の組織に血液が行き渡らなくなります。次に、押しつぶされた状態から解放されると、今度は血液が一気に流れ込みます。この時、筋肉の細胞が壊れてしまい、カリウムやリン酸などの物質が血液中に流れ出てしまいます。これが、高カリウム血症や急性腎不全といった、命に関わる危険な状態を引き起こします。
さらに、血液が再び流れ込んだ際に、組織が壊死してしまうこともあります。
治療としては、血液中のカリウム値を下げたり、腎臓の働きを助ける透析治療を行ったりします。また、腫れや圧迫を軽減するために、手術を行うこともあります。」
圧挫症候群とは

– 圧挫症候群とは
圧挫症候群は、地震などの災害時や事故に遭った際に、長時間、体の一部、特に腕や脚が重みで押しつぶされることで発症する危険な状態です。例えば、地震で倒壊した家屋や家具の下敷きになったり、交通事故で車に長時間挟まれたりすることで、この圧迫が発生します。
長時間圧迫されると、筋肉組織が損傷し、体内に有害な物質が流れ出すことがあります。そして、その有害物質が血液中に流れ込むことで、心臓や腎臓などの臓器に悪影響を及ぼし、様々な合併症を引き起こす可能性があります。
具体的な症状としては、腫れや痛み、感覚麻痺、壊死などが挙げられます。また、筋肉が壊死すると、ミオグロビンという毒性のある物質が血液中に流れ出し、急性腎不全を引き起こす可能性もあります。さらに、重症化すると、ショック状態に陥り、死に至るケースもあります。
圧挫症候群は、発症後の迅速な処置が重要となります。そのため、日頃から防災意識を高め、適切な行動をとれるようにしておくことが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 地震などの災害時や事故で、長時間、体の一部(特に腕や脚)が重みで押しつぶされることで発症する危険な状態 |
| 原因 | 倒壊家屋、家具、車両などによる長時間圧迫 |
| 体内への影響 | 筋肉組織損傷、有害物質の血液流入、臓器への悪影響、合併症 |
| 症状 | 腫れ、痛み、感覚麻痺、壊死、急性腎不全、ショック状態、死亡 |
| 重要性 | 発症後の迅速な処置、日頃からの防災意識と適切な行動 |
症状と原因

– 症状と原因
圧迫症候群の症状は、身体の一部が長時間圧迫されることによって現れます。 まず、圧迫されていた部分に腫れや痛みが生じます。 また、感覚が鈍くなり、しびれを感じることもしばしばあります。
重症化すると、筋肉細胞が壊死し始めます。 壊死した筋肉細胞からは、カリウムやミオグロビンなどの物質が血液中に流れ込みます。 これが原因で、高カリウム血症や急性腎不全といった、命に関わる危険な合併症を引き起こす可能性があります。
さらに、圧迫されていた部分の血流が再開した際に、注意が必要です。 この時、「再灌流障害」と呼ばれる現象が起こることがあります。これは、血流が再開することで、損傷した組織に酸素が供給され、活性酸素などが発生し、炎症反応などが起こることで、組織へのダメージがさらに深刻化してしまう現象です。 再灌流障害は、適切な処置を行わないと、後遺症が残しまう可能性もあるため、注意が必要です。
早期発見と治療
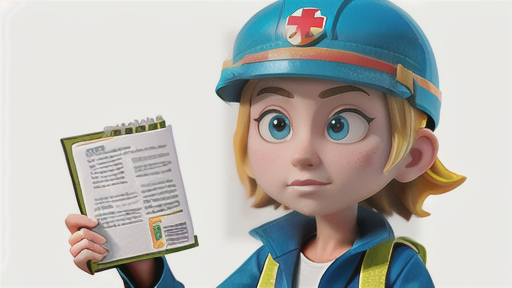
– 早期発見と治療
建物倒壊などの災害時、長時間体に重みが加わり続けることで、筋肉が損傷し、有害物質が血液中に流れ出す「圧挫症候群」を発症することがあります。この圧迫が長時間続くと、命に関わる事態に発展する可能性もあり、早期発見と適切な治療が非常に重要となります。
圧迫から解放された後、体のむくみや痛み、濃い色の尿が出現する、尿量が減少する、呼吸が苦しくなる、意識がもうろうとするなどの症状が見られた場合、直ちに医療機関を受診してください。一刻を争う状況であることを意識し、救急車を要請するなど、速やかな対応を心がけましょう。
医療機関では、体内の水分や電解質のバランスを調整するために、点滴による水分補給や電解質の補正が行われます。腎臓の機能が低下している場合は、人工透析が必要となることもあります。また、圧迫によって生じた腫れを抑えるために、患部を心臓よりも高く保ったり、冷却したりするなどの処置が行われます。
圧挫症候群は、適切な治療を行えば救命できる可能性が高い一方、発見や治療が遅れると、後遺症が残ったり、命を落としてしまう危険性もあります。そのため、日頃から防災意識を高め、圧挫症候群に関する正しい知識を身につけておくことが重要です。
| 症状 | 対処法 |
|---|---|
| 体のむくみや痛み | 直ちに医療機関を受診 |
| 濃い色の尿が出る | 直ちに医療機関を受診 |
| 尿量が減少する | 直ちに医療機関を受診 |
| 呼吸が苦しくなる | 直ちに医療機関を受診 |
| 意識がもうろうとする | 直ちに医療機関を受診 |
予防のために

「圧挫症候群」は、地震や事故といった災害時に、倒壊した建物や家具の下敷きになることで発症する危険性が高いものです。こうした事態に備えるためには、日頃から防災意識を高め、適切な予防対策を講じておくことが重要です。
まず、自宅や職場では、家具の転倒防止対策を徹底しましょう。具体的には、高い家具はなるべく低い場所に置き、転倒防止器具を用いて壁や床に固定することが有効です。また、寝室やリビングなど、長時間過ごす場所では、家具の配置を工夫し、万が一転倒した場合でも安全な空間を確保しておくことが大切です。
さらに、災害発生時の避難経路を家族や職場の同僚と共有しておくことも重要です。定期的に避難訓練を実施し、安全な避難場所や経路を把握しておくことで、落ち着いて行動できるよう備えておきましょう。
万が一、事故に遭い、体が挟まれた状態になった場合は、まずは身の安全を確保し、速やかに救助を要請することが大切です。そして、二次災害を防ぐため、周囲の状況をよく確認し、危険な場所には近づかないようにしましょう。
| 圧挫症候群の予防対策 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 家具の転倒防止対策 | – 高い家具は低い場所に置く – 転倒防止器具で壁や床に固定する |
| 安全な空間の確保 | – 家具の配置を工夫し、転倒しても安全な空間を確保する |
| 避難経路の共有と避難訓練 | – 家族や職場の同僚と避難経路を共有する – 定期的に避難訓練を実施し、安全な避難場所や経路を把握する |
| 事故発生時の対応 | – 身の安全を確保し、速やかに救助を要請する – 周囲の状況を確認し、二次災害を防ぐ |
